第九話 碧海の彼方(1)
かくして、アレッチェらペルー側のスペイン軍が英国艦隊を迎え撃つために臨戦態勢を整えるべく奔走している頃、当の英国艦隊は、まだ遠方にあったが、しかし、着実にペルー沖を目指して大海原を進んでいた。
今回、英国本国から当地に派遣された英国艦隊は、総指揮官ジョンストン提督の率いる主力2戦艦と補佐官パリアの率いる4戦艦、さらには、それらを援護すべく4巡洋艦と数艦の輸送船団が随行しており、全体で十数艦に及ぶ大船団を成す。
紺碧に輝く海原を、この時代、世界最強を誇る英国船団が堂々たる威光を放ちながら進みくるさまは、なかなかの壮観であった。
特に、此度の英国側の総指官たるジョンストン提督の乗る旗艦は、単独で70門以上の大砲を備えた轟々たる威力を有する強壮な軍艦であると共に、目にも麗しい当時の英国艦らしい優美さをも備えた戦艦であった。
当時は軍艦と言えども、碧海に映える美麗な帆船である。
高いマストに張られた無数の帆に吹きつのる海風を満帆に受けながら、煌く蒼い海原を間断なく疾走する、力感がありながらもスマートで優美な艦(ふね)…――。
そして、その美麗で重厚な艦に如何にも似つかわしい貫禄と威光を放つ一人の人物が、甲板に立っている――此度の英国艦隊総指揮官ジョンストン提督である。
今、提督が立つ甲板では、無数の水兵たちが、帆走の操作や訓練のために、ひっきりなしに走り回っていた。
いや、甲板のみならず、両舷横の舷側通路ぞいでも、金髪に陽光を反射させながら、日焼けした筋骨逞しい上半身を海風に晒した英国の水兵たちが、懸命に立ち働いている。
さすがに提督の乗る艦らしく、艦尾甲板の両舷には9ポンド砲の砲列が整然と並び、左右の舷側通路の下階には、一定の間隔をおいて、上甲板の18ポンド砲の砲列が、さらには、その下層の甲板には、主砲たる強力な32ポンド砲がズラリと並ぶ。
そして、それらの砲列の間を駆け回る水兵たちに命令を下す海尉たちの厳しいがなり声が始終止むことなく飛び交い、甲高く鳴る呼び子の音がけたたましく鳴り響いている。

一方、そんな汗臭く喧騒に呑み込まれた下界とは別世界のように、涼しい表情で颯爽と潮風を切り続ける艦首部分では、薄絹を美しい肢体に纏った黄金の女神像が、陽光を反射して眩く煌く。
さらに、そのまま視線を上方に移せば、軍艦旗を高く掲げる彫刻飾りの艦首楼が流れるように優雅な曲線を描き、その美観は、まるで宮廷のバルコニーさながらであった。
その豪華な艦首楼から、わざわざ降り来て、ジョンストン提督は、今、風上側のハンモック・ネッティング(註:甲板周囲に張られたネットで、戦闘時は弾除けにもなる)の脇にひとり離れて立ち、水兵たちの動きを厳粛な面差しで見下ろしている。
濃青色の長マントを纏い、陽光に輝く肩ほどの金髪を強風に吹きなびかせ、その厳格で凛々しい横顔では鋭い碧眼が光る。
年齢的には、そろそろ50代にさしかかる頃であろうか。
大艦隊を率いる提督なれば、水兵や海尉たちにとってはもちろん、艦内では神に等しき権力を有する艦長さえも頭の上がらぬ絶対的な権力を握る。
ジョンストン提督は、まさに、それに相応しき威厳と風格を兼ね備えた人物であった。

他方、そのような提督の威風堂々たる立ち姿を、艦尾楼にある豪奢なキャビンの一隅から、黒い僧衣に身を包んだアリスメンディが無言のままに見つめている。
それは、英国王室お抱えのイエズス会高僧。
此度の新大陸への進軍のために、相談役として英国王室から抜擢され、乗船している男である。
アリスメンディ――年の頃は提督よりも幾らか若く見えるが、風貌は、提督の金髪碧眼とは対照的に、短い黒髪に深遠な黒眼、そして、漆黒の僧衣に身を包んだ姿で、それは、どこか闇を纏ったような気配を湛えている。
僧というには、あまりに鋭い目をしており、危険な印象さえ与える。
それでいて、達観したような冷徹沈着な雰囲気も持つ人物であった。
少なくとも、爽やかな海風の吹き抜ける紺碧の背景が似合うタイプとは、言い難い。

このアリスメンディは、実はスペイン人で、かつてペルー副王領にてイエズス会の布教活動を行っていたところを、スペイン国王によるイエズス会弾圧によって本国からもペルーからも追放され、やむなく英国への亡命を余儀なくされたという暗い過去をもつ。
彼が追放されて、はや十数年の歳月が経つが、もともと戦闘的な性格であったこの人物は、スペイン本国への恨みを非常に強く持ち続け、それ故、スペインと敵対していた英国王室からは重宝がられてきた。
そのような男ゆえ、此度の新大陸におけるスペイン軍討伐にも、必ずや役立つであろうとの英国王室による采配による乗船であった。
実は、このアリスメンディは、かつて、かのアンドレスの父ニコラスの旧友でもあった。
今は亡きアンドレスの父も、生前はアリスメンディと同様にイエズス会に属し、スペイン本国からペルーに渡り来て布教活動をしていた人物であった。
そのニコラスは、インカ皇族の女性と運命的な出会いを経て、周囲の反対を押し切り、結婚。
生まれたのが、あのアンドレスであった。
当時、そのような日々の中、アンドレスの父であるニコラスは、布教と同時に、インカの民のおかれた窮状の改善と解放にも奔走していたが、そのような活動をスペイン国王から疎(うと)んじられた結果は、イエズス会の国外追放と暗殺という悲愴な末路であった…――。
それは、まだ、アンドレスが6歳になるかならぬかという、遥か幼き頃の話ではあるが……。
そのニコラスと共にインカの解放のために最後まで果敢に活動していたのが、同じイエズス会の神父であり知己の間柄でもあったアリスメンディであったのだ。
そのアリスメンディは、今、特権的階級の者しか踏み入ることのできぬ豪華なキャビンから続く艦尾楼の一隅から、甲板に立つジョンストン提督の方を感情の見えぬ眼差しで見下ろしている。
その視線を、ふと感じ取ったのか、ジョンストンは煌くような金髪と蒼いマントを潮風に吹き流しながら、艦尾楼の方をゆっくりと振り向いた。
当時の艦では、提督や艦長など重要なポストにある者たちの居住区やキャビンは、全て艦尾に備えられている。
それ故、艦尾楼もまた、宮廷のバルコニーさながらの精緻な彫刻を施された華麗な造りである。
その豪奢な艦尾楼の一角から、こちらを見下ろすアリスメンディの姿を認めると、ジョンストンは僅かに目を細め、無言の礼を払う。
黒衣を纏ったアリスメンディも、表情の変らぬ無機質な眼差しながら、提督に恭しく礼を払って応じた。
アリスメンディがキャビンに出てきていることを意識してか、ジョンストンは、ほどなく艦尾楼の方へ向かって戻りはじめた。
主に提督の領分であるこのキャビンは、先にも増して贅沢な造りになっており、船幅いっぱいの広大なスペースを有している。

空間の手前には、窓ごしに海を背景にした堅固なデスクが据えられ、中央には磨きぬかれた長テーブルがある。
そして、その上手にはカンテラの明りに光る壜類やデカンタ類が乗せられた盆が吊られ、艦の動揺につれて、ゆるやかに水平に揺れていた。
室内の戸棚や書棚は、いずれも格調高いマホガニー製で、その傍には上質なソファが置かれている。
一瞬、そこが軍艦の一部であることを完全に忘れさせる豪華さである。
だが、よく見れば、そのキャビンの両側には、さすがに軍艦らしく、帆布で覆われた9ポンド長砲がどっしりと据えられていた。
戻ってきたジョンストン提督は、キャビンの奥にいるアリスメンディに目礼すると、落ち着い動作で長マントを脱ぎ、ソファの脇にかけた。
マントを脱ぐと、青い軍服を身につけた、ガッシリと引き締った長身が現われる。
白い折り返した襟から覗く風貌は、厳然としつつも、碧海の勇者と言うに相応しい颯爽たる雰囲気を備えている。
彼は、赤味を帯びた光沢を放つ棚から、彫りの美しいカット・グラスを二つ取り出すと、ブランデーを注いだ。
そして、先ほどから、己の方をじっと窺うように見ているアリスメンディの方へと歩みゆく。
 一方、アリスメンディは、陽光に煌く海上には、到底、似つかわしいとは言えぬ影のような漆黒の僧衣に身を包んだまま、キャビン最奥にある艦尾の広大な窓々を背に立っていた。
一方、アリスメンディは、陽光に煌く海上には、到底、似つかわしいとは言えぬ影のような漆黒の僧衣に身を包んだまま、キャビン最奥にある艦尾の広大な窓々を背に立っていた。
それらの窓々は、塩の縞模様と波しぶきの斑模様とですっかり覆われており、一見、大聖堂のステンドグラスのように見える。
僧衣のアリスメンディとそれらの窓だけを切り取って見れば、その一角だけは、まるで別世界のようであった。
いつしか、窓の外には、夕刻時の気配が漂っている。
次第に強まる風と共に、戦艦の巨体が滑らかに加速していく。
ジョンストンは沈着な微笑みを湛え、「どうぞ」と、グラスの一方をアリスメンディに手渡した。
アリスメンディは、軽く瞼を伏せて礼を払い、それを受け取る。
やがて視線を上げたアリスメンディの闇のように黒い瞳と、ジョンストンの蒼く透明な瞳が、ゆっくりと合う。
「いよいよですな、提督」
地底を這うような低く硬いアリスメンディの声に、ジョンストンは僅かに間をおいて、頷いた。
「アリスメンディ殿、当地からスペイン軍を叩き出す好機を捉えてくれた貴殿には、感謝している」
アリスメンディは軽く頭を下げる。
「勿体無いお言葉でございます」
そんなアリスメンディの方に、ジョンストンはグラスをゆるやかに傾けた。
カンテラの明かりを反射して、グラスの端が鋭い閃光を放つ。

「この機会、何としても生かし切りたいものだ」
「はい…――」
再び畏(かしこ)まって見せながらも、鋭利な眼差しの変らぬアリスメンディを窺うジョンストンの目も、どこか探るように鋭い。
英国王室の信任が篤い高僧であることは知っているが、どこか腹に一物ありそうなアリスメンディに、直観力の鋭いジョンストンは、同船して日を重ねた今となっても、未だ全面的な信頼を置いてはいなかった。
(だが、このアリスメンディは、スペイン側の内情にも通じている上、過去には、あの新大陸の現地民との親交も深かったと聞く。
なれば、目的遂行のために、役立つ面もあろう…――)
ジョンストンは内心でそんな算段をしながら、感情の見えぬ目に、口元だけは笑みを湛えて、ブランデーのグラスを口元に運ぶ。
そのようなジョンストンの脇で、アリスメンディはグラスを飲み干すと、改めて、畏まりながら低く言う。
「提督。
密偵たちの報告によれば、これまで反乱軍のインディオたちは、ペルー副王領の隣国ラ・プラタ副王領を拠点として、反撃の機会を狙っていたとのことですが」
「うむ。
わたしもそのように聞いている。
だが、新大陸の内地の様子も、刻一刻と変わっているはず。
状況は、また推移しているに相違あるまい」

「はい。
可能でありましたら、一足はやく、わたし自身が密かに内地に入り、インディオたちと連絡を取るのが得策かと存じます。
スペイン軍を腹背から追い詰めるためには、早々にインディオたちと通じておくことが肝要かと」
「だが、下手な動きは、敵に出鼻をくじかれかねぬ」
言葉少なに、慎重な目つきで窓外に視線を動かすジョンストンに、相変わらず地底を這うような低い声でアリスメンディが言う。
「ご案じなさいますな、提督。
わたしは、かつて、ペルー側も隣国側も、くまなく布教に奔走した身。
地理にも、スペイン側の警護の手薄の場所にも、精通しております」
「うむ…とはいえ…――」
ジョンストンは、相変わらず難しい表情のままに、顎をさすりながら声を低める。
「我々に連絡してきたトゥパク・アマルが既に投獄されているとあっては、一体、インディオ側の誰と連絡を取るというのかね?」
アリスメンディは、色の見えぬ静かな微笑みを浮かべた。
「そのことですが、あのトゥパク・アマルは、脱獄したという噂もございます」
「!…――脱獄?!
では、トゥパク・アマルは生きて牢を出て、既に、反乱軍に合流しているのか?」
思わず身を乗り出した提督を、さりげなく牽制するようにアリスメンディは身を屈めた。
「いえ、提督、あくまで噂です。
真相は定かではありません。
たとえそうであったとしても、トゥパク・アマルは、まだ表には出てきていない様子」

アリスメンディの言葉を聴きながら、ジョンストン提督の厳格な横顔が、さらに険しくなる。
英国側にとっても、スペイン側にとってと同様、インカの民に対して絶大な影響力を持つインカ皇帝末裔なる存在が健在であることは、決して、望ましいことではなかった。
此度の戦闘では、スペイン側を新大陸から追い出した後、そのスペインに代わって新大陸を手中に収めたいのが英国側にとっての本音である。
トゥパク・アマルが囚われ、あるいは、処刑された後であった方が、新大陸へ覇権を広げるのは、遥かに容易であったはず。
そのような思考を馳せながら、提督は僅かに眉間に皺を寄せたまま、ブランデーのグラスを口元に運んだ。
やや不機嫌になった声音で、提督が冷ややかに問う。
「ならば、いずれにしろ、表には出ていないトゥパク・アマルとの連絡は不可能であろう。
アリスメンディ殿、貴殿はインディオ側の誰と連絡を取るというのか?」
「はい。
少々、縁ある相手がおりまして……。
それも、トゥパク・アマルと関係の深い人物でございます」
「では、その者と連絡を取ると?」
「はい。
提督がお許しくだされば、すぐにも出立いたしたく」
「それで、その相手とは誰なのだ」

「トゥパク・アマルの甥にあたる者でございます」
「トゥパク・アマルの甥?」
「アンドレスというインディオ側の将の一人でございます。
まだ、年は若いとは思いますが」
「アンドレス?」
ジョンストンの手にあるカット・グラスが、揺れるカンテラの光を反射して鋭く光る。
「そのインディオの若者と貴殿に――縁がある、とは?」
「はい、提督」
アリスメンディは鋭利な目元を僅かに伏せて、やや間を置くと、漆黒の瞳をジョンストンの方にゆっくり動かしていく。
「かつて、わたしがペルー副王領にてイエズス会の神父として活動していた頃、共に布教を行なっていた者がおりました。
わたしにとっては、友であった者でもあるのですが……。
いずれにせよ、アンドレスはその者の息子なのです。
ただ、母親がインカ皇族の末裔であるため、あのトゥパク・アマルとも何かと関係が深いというわけです」
「では、そのアンドレスとやらは、生粋のインディオではないということか…!
そのような者が反乱軍を率いているとは」
「確かに、アンドレスは混血児ではありますが、父親を早くに亡くしているため、完全にインカ側の人間として育てられたものかと。
しかも、トゥパク・アマルとも近しい環境で育ってきておりましょうから、さぞやスペイン側には敵対心を強く持っておりましょう……」
アリスメンディは、かなり薄暗くなってきた窓外に視線を走らせると、再び、ジョンストンの方に身を屈めた。
「それに、この状況に至るまでには、その若者も、自分の父親とわたしとの関係について、幾らかは聞き及んでいるものと思われます。
そのぶん、話はつけやすいかと」
「なるほど…」
ジョンストンは思慮深い眼差しでグラスを机上に置くと、長く強靭な指を組んだ。
そのような提督の前で、アリスメンディは、やや前傾姿勢になりながら、低い声で囁くように続けていく。
「スペイン側の臨戦態勢が進めば、内地にしのびこむのも難儀となりましょう。
ですが、今なら…。
この艦隊が、まだペルー沖から遠方にあるため、敵の警護の手薄な場所もあろうかと。
今のうちなら、インディオのために持参した武器も小型船に分散して乗せ、少人数であれば、密かに陸に近づき上陸することも可能かと存知ます。
わたしは、海上ルートも、内地のルートも、熟知しております。
どうか、わたしにお任せください」
「アリスメンディ殿、インディオたちに運んできた武器は、あくまで内地のスペイン軍を彼らに叩かせるためのもの。
此度の戦、インカ軍がどれほどスペイン軍を圧倒できるかが、我々の勝利にも大きく関わってくる。
もちろん、最終的には、我々はインカ軍も叩き潰さねば、意味はないが」
「…――提督のお心は、よく分かっております」
「うむ」
ジョンストンは、まだ難しい顔をしつつ一呼吸置きながらも、ついに頷く。
「分かった。
アリスメンディ殿、インディオとの連絡、そなたに任せる」
「ありがたき幸せに存じます。
では、早速にも、今宵、出立いたします…――」
茜色に染まる空を紅く映す壮麗な艦尾窓を背に、黒いシルエットを纏ったアリスメンディは、深く礼を払って静かに微笑んだ。
日暮れと共に、アリスメンディの一団は英国艦隊の本隊を離れ、いち早く陸を目指した。
インカ軍に渡すために英国から運ばれてきた武器類も、アリスメンディ率いる小船団に分散して乗せられ、共に運ばれていく。
分隊した彼らを運ぶ小型艇は、提督の乗る巨大な旗艦よりも大分小ぶりであるが、その分、走行速度が速く、小回りも効く。

アリスメンディは艇の甲板に立ち、次第に離れゆく英国艦隊の大船団を眺めやった。
艦隊の中央を帆走する提督の旗艦――その艦首から、次第に最奥の艦尾楼の方まで視線を動かしていく。
先刻まで提督と共に語らっていたキャビンの窓から、微かな灯りが漏れている。
アリスメンディは、冷ややかに目元を細めた。
(新大陸から奪うことばかりを考えている者たちよ―――…)
それから、彼は前方へと向き直る。
まだ陸からは遥か離れた洋上ではあったが、船の向かう進路の先には、アンデスの霊峰が連なる長大な大陸が広がっていることであろう。
雲間から差し込む月明りを浴びて、漆黒の僧衣が白い光を帯びながら強風の中に翻る。
不意に、アリスメンディの傍に、英国の水兵が近づいた。
海尉の一人と思われるその男は、アリスメンディの方へ機敏に礼を払うと、闊達な口調で言う。
「アリスメンディ様、此度の分隊に同行させて頂くことになりました!!
どのようなご指示でも、何なりとお申し付けください!!」
アリスメンディも軽く礼を払うと、低く問う。
「陸までは、どれ位かかりそうか?」
「はっ!!
この船なら、本隊よりはかなり早く到着できるものと思われますが、それでも10日以上はかかるかと」
「そうか…」
「アリスメンディ様、このまま直にペルー沖を目指しますか?」
「いや」
船の加速に伴い、アリスメンディの僧衣の裾がバサバサと激しい音を立ててはためきだす。
「ペルー沖を迂回して、スペイン軍の監視の手薄いラ・プラタ副王領側の沿岸沿いから上陸の機会を狙う」
「分かりました!!」
再び礼を払って水兵が勢いよく立ち去ると、甲板上には、吹きすさぶ風の音のみの世界が舞い戻る。
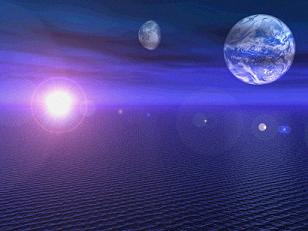
アリスメンディは、突き刺すような風の中で、真っ直ぐ前方を見つめた。
まだあまりに距離が離れていて、ありえるはずもないことだが、潮風に混ざって、アンデスの雪の、土の、風の匂いが流れてくるような気さえする。
彼は、静かに瞼を閉じた。
そして、胸元の十字架を握り締める。
(ニコラス…そなたの眠る地に戻ってきたぞ―――…)
かくして、アリスメンディが遥か離れた洋上から見つめていた先には、まさしく南米の雄大な大陸が広がっていた。
その南米大陸の沿岸線の形状に添って、雪を冠したアンデスの霊峰が厳然と連なり渡っている。
そして、それら連綿たる山脈の中腹には、非常に大規模で、見るからに堅固なインカ軍本隊の陣営が、堂々たる威光を放ちながら展開していた。
その姿は、まるで巨大なコンドルが、逞しく強靭な漆黒の翼を広げ、自ら盾となり、アンデスの霊峰を守っているかのごとくである。

澄んだ深藍色の天空では、氷の欠片のような無数の星々が煌き、下界の陣営に繊細な光を降り注ぐ。
一方、そうした星灯りを圧倒する勢いで、陣営の随所では太い松明の炎が激しく燃え上がり、火の粉を巻き上げながら、夜闇を熱く焦がしていた。
そして、その陣営の中央には、見るからにガッシリと頑強に組まれた広大な天幕がある。
ひときわ眩い松明に照らし出された天幕の周囲では、剣や銃で武装した無数の厳ついインカ兵たちが、野性的な眼を光らせている。
今、天幕の内部では、インカ軍総指揮官トゥパク・アマルが、副官ディエゴと護衛のビルカパサを筆頭に、主要な隊長たちと共に地勢図を囲んで座していた。
この頃、トゥパク・アマルは既にマチュ・ピチュを下り、副将ディエゴにあずけていたインカ軍本隊と合流をはかっていた。
彼は、強い恍惚と緊迫感の漲る天幕の中央で、英国艦隊到来に向けて、廷臣たちと共に軍議に臨んでいる。
白い上質なシルクの上衣にかかる絹のような漆黒の長髪は、燭台の灯りを受けて濡れたように輝き、研ぎ澄まされた端整な横顔で、やや下向き加減になった切れ長の目は静かな光を宿している。
その纏う静寂なたたずまいは、瞬間、そこが陣営の中であることを忘れさせるほどだが、しかし、ゆっくりと正面に向き直った視線は、射るように強く、鋭い。

「それで、英国艦隊の規模は、いかほどか?」
あのトゥパク・アマルの低く響く声に、彼の脇に座していたディエゴが、「はっ!!」と深く礼を払って応ずる。
ディエゴは岩のような厳つい手で素早く書類を繰りながら、トゥパク・アマルの方に体ごと真っ直ぐ向いた。
「此度の英国艦隊の規模ですが、多方面からの情報を総合して推測するに、旗艦を含めて少なくとも6戦艦、さらに巡洋艦が4〜5艦、他にも輸送船が多数同行しているものと見込まれます!!」
「そうか」
思慮深げに再び伏せがちになったトゥパク・アマルの面差しに、周囲の者たちの視線が、その表情の意味を読み取ろうとするかのごとく、じっと集中する。
彼らの目に映るトゥパク・アマルの表情は、いっそう険しくなっているようにも見え、それでいて、僅かに微笑んでいるようにさえ見える。
長い沈黙の後、ついに痺れを切らしたように、ディエゴが、その巨体を乗り出した。
「あの、トゥパク・アマル様…」
「うむ。
そこそこの規模ではあるが―――」
トゥパク・アマルは美麗な顔を上げると、ディエゴに、そして、周囲に視線を走らせ、低く言う。
「英国艦隊も、内地の我がインカ軍がスペイン軍を叩きのめしてくれんことを、さぞや、期待していることであろう」

トゥパク・アマルの方を見据えたまま、ディエゴが再び口を開いた。
「トゥパク・アマル様。
此度の英国艦隊には、あのイエズス会のアリスメンディ殿が同行されているという噂もございます」
「そうか。
アリスメンディ殿が、当地に戻って来られるか…――!」
トゥパク・アマルの深遠な瞳が、光を強めて見開かれる。
彼は、その強靭でしなやかな褐色の指先で、地勢図を引き寄せた。
「それで、英国艦隊の到来しそうな場所は?」
「はっ!!
やはり、アレキパ界隈ではないかと」
ディエゴの言葉を聴きながら地勢図全体を鋭く見渡すトゥパク・アマルに、共に座していた中の一人の隊長が畏まって問う。
「畏れながら、トゥパク・アマル様。
スペイン軍は、既にアレキパに布陣をはじめているもようです。
急ぎ、我が軍も分遣隊を向かわせますか?」
トゥパク・アマルは真摯な眼差しで、そちらを見やった。
「スペイン軍を破って英国軍が上陸してくる事態ともなれは、我が軍が英国軍の侵入を阻止せねばならぬ。
そのような事態に備え、アレキパの周辺地域に派兵は行う。
ただし、海上での英国艦隊討伐については、スペイン軍に委ねてこそだ。
おおかた、スペイン軍にとって、海岸線に近いアレキパは重要な補給基地ともなろう。
英国軍、スペイン軍共に、最大限の力でぶつかり合ってもらわねばならぬ故、当面は、我が軍はアレキパには手出しはせぬ」
「はっ!!」

恭順を示す廷臣たちの前で、トゥパク・アマルは再び地勢図を視線でなぞり、険しい表情で続ける。
「この事態となっては、さすがに民の間にも、英国艦隊到来の噂が流れはじめる頃であろう。
流言とは、往々にして、人の不安をいたずらに煽りやすきもの。
これからという、この大事な時に、下手に民の足並みが乱れれば、命取りにもなりかねん。
わたしも、こうして身を隠してばかりもおられまい。
そろそろ潮時かもしれぬ―――」
「はっ!!
トゥパク・アマル様!!」
いっそう深々と恭順を示す廷臣たちに、トゥパク・アマルも切れ長の目を細め、鋭く頷き反した。


